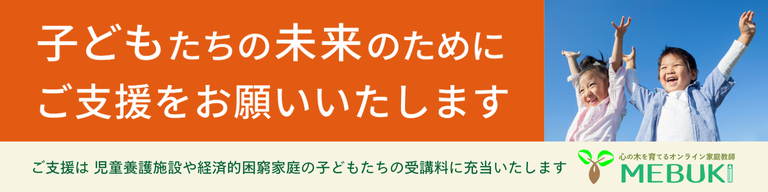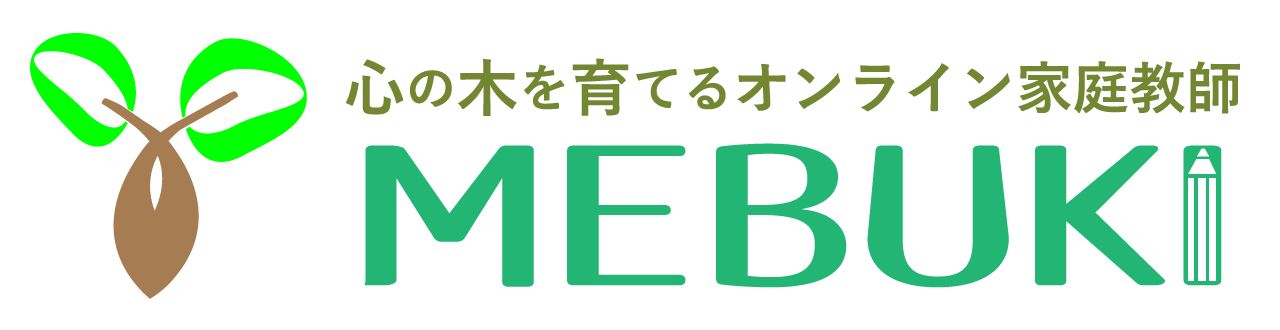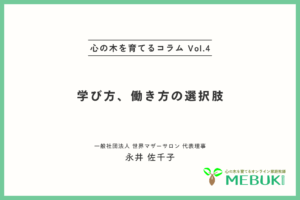心の木を育てるコラム vol.5 幼少期に大切にしたいのは「穏やかに過ごすこと」
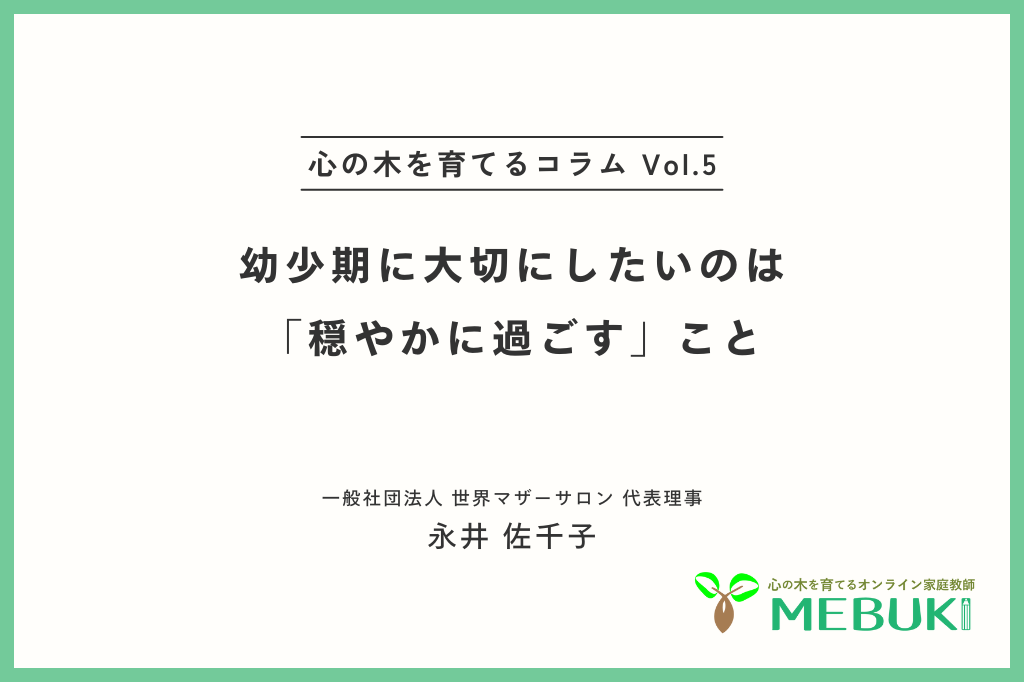
「オンライン家庭教師MEBUKI」は、一般社団法人世界マザーサロンの『心の木を育てよう』をベースとした、対話を通して子どもたちの「心」をととのえながら学習を進めるプログラムです。
MEBUKIの講師は、“心の木”の考え方や子どもたちとの関わり方について定期的に研修を受け、お互い学び合いながら、質の向上に努めています。子どもたち、そして保護者の方にとっても、安心・安全な場を作ることを何よりも大切にしながら、丁寧に関係を築いていきます。
幼少期に大切にしたいのは「穏やかに過ごすこと」

世界マザーサロンは「オンライン家庭教師MEBUKI」の他、若者の居場所兼就労支援「学び舎めぶき」も運営しています。「学び舎めぶき」では、最近小さいお子さんをお持ちの親御さんから相談されることが増えてきました。
乳児検診では「ちゃんとやる」ことを指導され、成長が「標準」から外れていると過剰に心配されてしまい、検査を受けた方が良いのではと言われる。
専門家に指摘されたら、誰だって不安にもなります。
みんな一緒、みんなと同じように、という考えは、学校教育から始まっているわけではなく、子どもを産んだ瞬間から「普通はこう」のマインドが植え付けられてしまっている、ということを改めて感じました。
「あれもこれもしっかりと、と言われてしまいどこで手を抜いたら良いか分からない」と言われていた方がいました。
SNSで綺麗な離乳食が出ていれば、ここまでやらないといけないのか、、と感じてしまったり、早期教育が大切!というCMを見れば早くやらないと力を伸ばせないのでは・・・と思ったり。
これまで私自身の子育てや日々の活動を通してずっと思っていることは、幼少期、特に3歳までの時期で大切にしたいことは、「穏やかに過ごす」ということだけ。
心のストレスをできる限り排除する。
この時期の子どもの欲求はそんな大したことではありません。
もっと遊びたい、とか、もっと抱っこしたいとか、本能に基づくもの。
その欲求を大人の都合で諦めさせないといけない状況になってしまうから、ストレスが溜まってしまう。
もちろん大人も忙しいので、受け止め続けるのも難しいことはあると思います。もしかしたら発達特性により、「育てにくさ」を感じてしまう子もいるかもしれません。でも、それを最初から「無理」としてしまったら何も変わりません。
穏やかに過ごすことを考えた時、今何が大変なのか、生活で変えられることは無いか、誰かの助けを得られないか、もっと考えていけると良いのかなと思います。
他の子と比べる必要はなく、今、目の前の子が穏やかに過ごせること。
力が抜けた状態になっていれば、子どもは自分で道を切り拓いていけます。
他の子と比べて「こうしなければ」とがんばる必要はなく、ただただ一緒に穏やかに過ごす。
そんなことを親御さんたちともっと話していけたらなと思います。
一般社団法人 世界マザーサロン
代表理事 永井佐千子
これからの時代を生き抜く力を育む教育の実践
学び舎めぶきでは、岡田武史さん、そして、めぶきの活動を当初より応援いただき、岡田さんをめぶきにおつなぎいただいた「キヤノングローバル戦略研究所 」研究主幹の 瀬口清之さんに、その後の学び舎めぶきの現状や課題をご報告させていただく機会を設けさせていただきました。
テーマは「これからの時代を生き抜く力を育む教育の実践」 主体性を育む、教育に東洋思想的視点を、心の土台づくりなど、様々な切り口から、これからの教育についてお話をうかがいました。
対談の模様はYouTubeでご覧いただけます。
今の時代にこそ学びたい、東洋思想の本質と教育現場への活かし方
学び舎めぶきでは、ひきこもっている若い人たちが、「自分の人生を愉快に生きていく力をつける」ことを目指して、様々な活動を行っています。
この度、キヤノングローバル戦略研究所 瀬口清之さん、元広島県教育長 平川理恵さんをゲストにお招きし、東洋思想をテーマに鼎談を開催いたしました。
テーマは「今の時代にこそ学びたい、東洋思想の本質と教育現場への活かし方」。東洋思想を様々な角度から実践されているお二方のお話から、たくさん学ばせていただきました。
鼎談の模様はYouTubeでご覧いただけます。
心の木を育てるコラムバックナンバーはこちらからご覧いただけます。
vol.1 「決めつけない関わりと、大人同士のつながりを大切に」
vol.2 「社会と学校が離れすぎている~誰もが安心して生きていける社会に」
vol.3 「なぜ高校に進学するのか」
vol.4 「学び方、働き方の選択肢」
こちらからお気軽にお問合せください。
オンライン家庭教師MEBUKIでは、どのような環境に置かれている子でも受講ができるよう、経済的に厳しいご家庭の方には補助制度を導入しています。皆様からのご寄付は、そうしたご家庭の授業料に充当いたします。
社会全体で子どもたちの未来をサポートしていけたらと思います。ぜひ、皆様からの温かいご支援をよろしくお願い致します。